


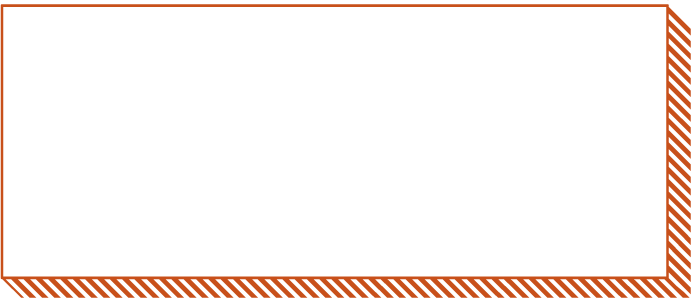
日本女性初の一級建築士となった桜蔭会会員:浜口ミホ氏ーダイニングキッチンの生みの親
2025.4.26
2年ほど前に放送された「キッチン革命」というドラマを覚えていらっしゃいませんか?浜口ミホ氏をモデルにした“浜崎マホ”が、建築家として、日本の台所を大改革するために奮闘するストーリーで、伊藤沙莉さんが主演されました。「虎に翼」の前ですね。
浜口ミホ氏(昭和12年、東京女高師家事科卒 旧姓浜田)は、卒業後に東京帝大工学部建築学科の聴講生となり、昭和29年に女性初の一級建築士となった桜蔭会会員です。
昭和になっても戦後になっても、私の祖母くらいの年代の女性達の使っていた台所は、北側や土間の低いところにあり、水道こそありましたが、流しは、研ぎ石のようなコンクリートっぽい、灰色のものでした(私はしばしばそこで蛞蝓さんと遭遇しました)。暗くて寒い、じめっとした北側に追いやられ、使い勝手の悪い設備を使い、女性たちが苦労する場でした。そんな台所を、家族が食事を楽しむ家の中心へと移動させ、設備も流し台や調理台を、清潔で美しいステンレスに、作業動線を考えた横一列並びにというアイデアを実行させたのが浜口氏でした。
子供たちは学校から帰ると真っ先に台所に飛び込んで「おなかすいた、なんかない?」。宿題も食卓でして、親は台所仕事をしながら、それにつきあうことができるようになったのです。男性だって“厨房に入って”お皿洗いくらいはできるようになりました。
アイデアはそのころ建設がはじまった日本住宅公団の団地で生かされ、“ダイニングキッチン”の思想が、憧れとして団地以外の住宅にも広まっていきました。なるほど“革命”と呼ぶにふさわしいですし、そこには家事というものに対する確固とした思想が感じられます。
浜口先輩をもっと知りたくなりませんか?
そこでお知らせです。このたび、佐々木泰子学長先生が中心となって、今年150周年を迎える本学の記念シンポジウムとして
「イノベーションはどのように創られるか~お茶の水女子大学の歴史から考える~」
【日時】2025年5月9日(金)15:00~17:00
を企画され、佐々木泰子先生をはじめ、東京科学大の塚本由晴先生もパネリストとしてご登壇いただけるそうです。詳しくはこちらをご覧ください。
浜口ミホ氏が設計した住宅が現存していることを、塚本由晴研究室の卒業生であるノエミ・ゴメス・ロボ博士が発見して、保存に尽力していらっしゃるそうです。写真で見ると、レトロモダンな、美しい住宅です。余談ですが、その住宅に使用されている美しい釉薬のタイルと同じものが名古屋市内の老舗喫茶店「コンパル大須本店」に使われているとのことで、名古屋出身の私としては何回も通った“サテン”なのでびっくりし、急に親しみも感じています。
参考文献:黒田光太郎2022「日本の工学教育への女性の参加―工学部の初期女子学生-」公益社団法人日本工学教育協会2022年度工学教育研究講演会講演論文集 ほか
桜蔭会 会長 髙﨑みどり

